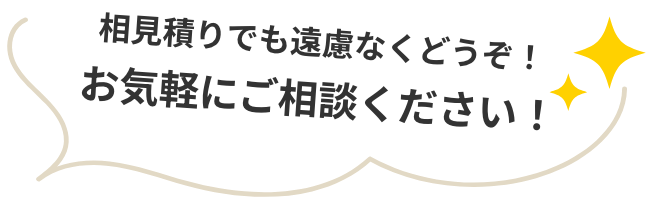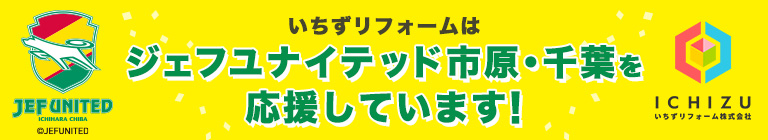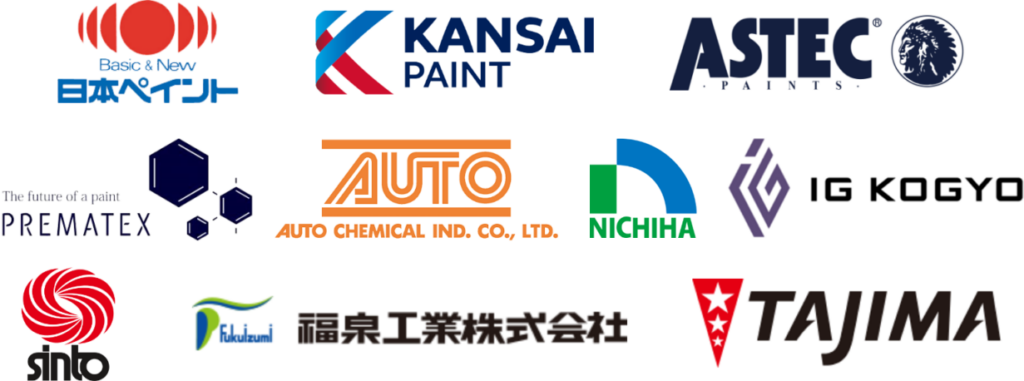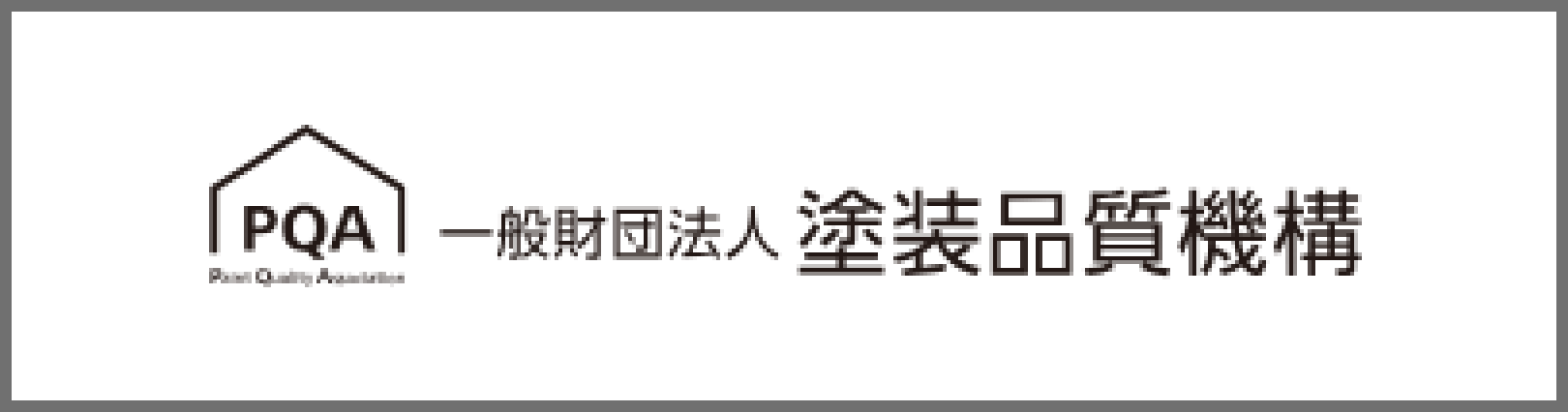市原市ちはら台西D様邸②屋根ビス|陶器平板瓦のビスコーキングの必要性とは?

皆さんこんにちは!
前回に引き続き、千葉県市原市ちはら台西D様邸のレポートです。
今回は屋根のビスコーキングの様子をご紹介!
棟瓦やケラバ部分のビスを締め直し


D様邸の屋根は陶器平版瓦で、基本的に塗装は不要です。ただ、瓦を固定するビス(ねじ)に緩みがあったので締めなおしました。
また、今後のゆるみ防止のためにシーリングで固定していきます。
そもそもビスコーキングとは?
瓦を固定したビス頭の部分にシーリング材(コーキング材)を充填し、防水性を高める処理のことを指します。陶器平板瓦の場合、ビスでしっかりと留める施工が一般的です。
しかし、固定したビスの周りにはわずかな隙間があり、その部分から雨水が浸入してしまう可能性があるのでシーリング材で完全に塞ぐというわけです。

ビスコーキングの施工の流れ
- 瓦をビスでしっかりと固定する
- ビス頭部分をきれいに清掃する
- 屋根用の耐候性シーリング材を充填する
- 表面を均一にならして仕上げる
シンプルな作業ですが、使用するシーリング材の種類や充填量によって耐久性が大きく変わります。
屋根の色に合わせて茶色のシーリング材をチョイスしました。細かな点もこだわってしあげるのがいちずのモットーです^^
なぜビスコーキングが必要なの?
- 雨漏り防止のため
陶器瓦自体は雨を通しませんが、瓦と瓦の重なりや固定ビスの部分は弱点となります。とくに豪雨や強風時には、雨水がビス穴から侵入するリスクがあります。ビスコーキングを施すことで、そのリスクを大幅に減らせます。 - ビスの劣化を防ぐため
露出したビスは雨水にさらされるとサビやすく、固定力が落ちる原因となります。コーキングで覆うことでサビや腐食を防ぎ、屋根全体の耐久性を高めます。 - 風による被害を抑えるため
台風や強風で瓦が浮き上がろうとした際、ビスがしっかり効いているかどうかで被害の大きさが変わります。ビスコーキングは瓦を長期的に安定させる役割も担っています。
棟瓦やケラバ瓦のビス一つ一つをシーリング処理



屋根のてっぺんにある瓦を棟瓦(むねがわら)、端っこにある瓦をケラバ瓦と呼びます。一つ一つのビスをしっかりとシーリングで固定しました。
D様邸の屋根ビスコーキングが完了しました!

陶器平板瓦は長持ちする屋根材ですが、「固定ビスの防水処理」を怠ると雨漏りや劣化の原因になってしまいます。ビスコーキングは小さな作業に見えて、屋根の寿命を左右する大切なポイントです。
「新築から10年以上経った」「最近、瓦屋根の点検をしていない」という場合は、一度専門業者に相談してみることをおすすめします!
次回はシーリング打ち替えの様子をお届けしますのでお楽しみに!
最後までご覧いただきありがとうございました(^^)/
/ S /